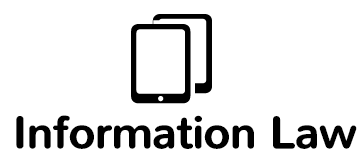記事内容の真実性を誤信した場合の名誉毀損罪の成否-夕刊和歌山時事事件

前回の記事で、民事訴訟における相当性の理論について最高裁判例を紹介したが、刑事裁判ではどうなっているのかを略してした。今回それを補足しようと思う。
Contents
名誉毀損罪の構成要件と法定刑
名誉毀損罪は、刑法230条1項に次のように規定されている。
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
法定刑
名誉毀損罪は親告罪(刑法232条)とされているので、被害者の告訴(刑事訴訟法230条)または死者の親族または子孫の告訴(同233条)がなければ、起訴することはできない。
告訴があり、名誉毀損罪で起訴され、裁判所が名誉毀損罪の成立を認めた場合、1月以上3年以下の懲役または禁錮か、1万円以上50万円以下の罰金のいずれかが言い渡される(刑の下限は、刑法12条、13条、15条に規定されている)。
検察統計によれば、名誉毀損罪の起訴件数は1990年代では年間数十件であったが、2000年に入ってからは百件台にのぼり、2013年には約200件代まで増加している(検察統計2013年「罪名別被疑事件の未済及び既済の件数」)。たとえば、2015年の検察統計の「罪名別被疑事件の未済及び既済の件数」によると、名誉毀損罪の起訴件数は、生存している者に対する名誉毀損として236件(公判請求90件、略式命令請求146件)、死者に対する名誉毀損として229件(公判請求90件、略式命令請求139件)となっている。名誉毀損の内容が記載されているわけではないので、詳細は不明であるが、おそらくインターネット上の名誉毀損の増加が影響しているものと思われる。
名誉毀損というと、報道機関に対する民事裁判を思い浮かべるが、刑事事件としても多数の事件があり、それがインターネット上の表現で行き過ぎがあれば、誰でも名誉毀損罪の被告人となりうることについては留意しておく必要があろう。
構成要件
名誉毀損罪が成立するためには、表現行為が
①公然と
②事実を摘示し
③人の名誉を毀損したこと
が必要となる。
①②③は法律用語で構成要件と呼ばれている。構成要件とは、犯罪として処罰される行為を類型化したものをいい、犯罪が成立するためには、まず、ある行為がいずれかの構成要件に該当する必要がある。
①の「公然」とは、不特定または多数人が知ることのできる状態におくことをいう。
②の「事実を摘示」するとは、具体的な事実を要約して示すことをいう。事実は真実であるか虚偽であるかを問わない。もっとも、刑法230条2項は、「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」と定めており、死者について摘示した事実が真実である場合には、名誉毀損罪は成立しない。
③の「名誉を毀損する」とは、人の価値に対する社会的評価を低下させることをいう。
違法性阻却
さて、犯罪は構成要件に該当しただけで成立するわけではなく、その行為が違法かつ有責である必要がある。
名誉毀損罪についていえば、刑法230条の2に該当する場合には、違法性が阻却され名誉毀損は免責される。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
すなわち、名誉毀損行為とされる表現について、
①公共の利害に関する事実であること(公共性)
②もっぱら公益を図る目的があること(公益性)
③摘示された事実が真実であること(真実性)
を証明した場合には、違法性がなく犯罪が成立しないのである。
①の公共性については、何が公共の利害に関する事実にあたるかが問題となるが、刑法230条の2の2項・3項は次のように規定している。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
つまり、起訴前の犯罪行為や公務員や公職者に関わる事実は、公共性が認められる。起訴前の犯罪行為に公共性が認められる以上、起訴後の裁判にも公共性が認められるのは当然といえよう。これら以外にも社会的な関心事には公共性が認められることが多い。
難しいのは私人の私生活上の行状であるが、これも「そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては」公共性が認められる場合がある(「月刊ペン」最判昭和56年4月16日)。
②の公益性については、主たる動機が公益を図る目的であればよいと一般に考えられている。
①の公共性と②の公益性の証明は、合理的な疑いを容れない程度に検察官が行うが、問題は③の真実性である。こちらは例外として、被告人が真実であることを証明する責任を負う。
被告人が証明責任を負うことについての疑問についてはこちらへ 「報道した事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには名誉毀損は成立しない―署名狂やら殺人前科事件」
夕刊和歌山時事事件
それでは被告人が真実であることを証明できなかった場合は、即有罪となってしまうのだろうか。もしそうであれば、処罰をおそれて萎縮し、確実に真実であることをつきとめなければ報道ができなくなってしまいかねない。そこで一定の場合に免責を認めたとされるのが、夕刊和歌山時事事件の最高裁1969〈昭和44〉年6月25日大法廷判決である。
事案の概要
被告人は、和歌山時事新聞社を経営し、「夕刊和歌山時事」を編集・発行していた。他方、Aは「特だね新聞社」を経営し、旬刊「和歌山特だね新聞」を編集・発行していた。第1審判決によると、和歌山特だね新聞は、他の新聞に書かれないような、あるいは他の新聞があえて取り上げないような特だねをできる限り書くことを編集方針としていて、道義的に不正、不義な事柄の摘発、暴露攻撃の記事を主とし、読者が低俗な興味をもってとびついてくるような見出しの工夫をしていたという。Aは、恐喝、名誉毀損罪により有罪判決を得たことがあり、人の名誉、信用を毀損するような記事等を掲載したこともあった。
被告人は、以前からそのようなAの特だね新聞の在り方に対し、社会の公器たる新聞の使命にもとるものとして厳しく批判されるべきと考え、夕刊和歌山時事に批判の記事を執筆していた。すると、Aは自身が入会を拒否された和歌山の新聞協会や夕刊和歌山時事を誹謗し、不当な記事を書きたてたりした。それが契機となって、被告人はAを徹底的に批判する記事を書くことにした。
被告人は、1963〈昭和38〉年2月、夕刊和歌山時事に、「街のダニAの行状」、「吸血鬼Aの罪業」と題する記事を自ら執筆して7回にわたり連載した。その記事の中で、A本人またはAの指示のもとに、和歌山特だね新聞の記者が和歌山市役所土木部の課長に向かって「『出すものを出せば目をつむってやるんだがチビリくさるのでやったるんや』と聞こえがしの捨て科白を吐いたうえ、今度は上層の某主幹に向かって『しかし魚心あれば水心ということもある、どうだお前にも汚職の疑いがあるが、一つ席を変えて一杯やりながら話をつけるか』と凄んだ」と書いた。
被告人は、この記事内容について名誉毀損罪に問われ、和歌山地方裁判所で罰金3000円の判決を受けた。同判決によると、記事は、①土木部の某課長に向って「出す物を出せば云々」の暴言を吐いた旨の事実と、②上層の某主幹に向って「しかし魚心あれば水心云々」と凄んだ旨の事実の2つを摘示しているとし、この摘示事実をめぐって名誉毀損罪の成否が争われた。
被告人は、夕刊和歌山時事の編集長その他従業員が取材し、メモあるいは口頭報告によって提供された資料をもとに執筆したという(第1審判決は、①の摘示事実についての資料は伝聞によるるもので簡単なものであることや、②の摘示事実についての資料は直接取材に基づくものであるが、その内容と実際に摘示した事実とが異なることなどを述べて、資料の事実的判断や価値判断を過失によって誤ったと判断)。
第1審判決に対し、被告人は、「証明可能な程度の資料、根拠をもつて事実を真実と確信したから、被告人には名誉毀損の故意が阻却され、犯罪は成立しない。」旨を主張し控訴した。
大阪高等裁判所は、「被告人の摘示した事実につき真実であることの証明がない以上、被告人において真実であると誤信していたとしても、故意を阻却せず、名誉毀損罪の刑責を免れることができないことは、すでに最高裁判所の判例(昭和34年5月7日第一小法廷判決、刑集13巻5号641頁)の趣旨とするところである」と判示して、被告人の主張を排斥し、たとえ被告人が真実であると誤信したことにつき相当の理由があったとしても名誉毀損の罪責を免れ得ないとして、控訴を棄却した。
そこで被告人は、最高裁に上告をした。
最高裁は、弁護人の上告趣意は憲法21条違反をいう点もあるが、実質は法令違反の主張であり適法な上告理由にあたらない、としながらも、職権で検討し、原判決および第一審判決を破棄し、事件を和歌山地方裁判所に差し戻した。
判旨
刑法230条の2の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法21条による正当な言論の保障との調和をはかったものというべきであり、これら両者間の調和と均衡を考慮するならば、たとい刑法230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。これと異なり、右のような誤信があつたとしても、およそ事実が真実であることの証明がない以上名誉毀損の罪責を免れることがないとした当裁判所の前記判例(昭和33年(あ)第2698号同34年5月7日第一小法廷判決、刑集13巻5号641頁)は、これを変更すべきものと認める。したがって、原判決の前記判断は法令の解釈適用を誤ったものといわなければならない。
事件の顛末
事件は和歌山地裁に差し戻されたが、地裁で再度有罪の判決があり、被告人は控訴したが棄却され、有罪が確定している。
最高裁判決が出るまで
下級審の判決は、早くから真実性の証明がない場合であっても、行為者が真実と信じ、健全な常識に照らして真実と信じるのが相当と認められる程度の客観的情況がある場合には、名誉毀損の故意が阻却され、犯罪は成立しないとするものが多かった。しかし、上記判旨にあるように、最高裁は、1958〈昭和33〉年の判決で、真実と証明されない限り処罰は免れないと判断した。
現在、最高裁の判決が出ると、下級審の判決は最高裁の判決にならって判断をするものが多いように思われる。しかし、この頃の下級審はそうではなかったのか、最高裁判決が出た後も、従来と同様の判決が出される傾向にあった。
この判決の3年前に遡ると、最高裁は小法廷の決定ではあるが、民事裁判で先んじて相当性の理論を認めるに至っていた(署名狂やら殺人前科事件)。
こうした経過の中で、本件の最高裁判決が出されたわけである。
最高裁判決後の流れ
相当性は厳しく審査
この判決後が出た当時は、おそらく刑事免責の範囲が広がり、公共性のある事項について表現の自由がより保障されるという期待があったであろう。残念ながら、その後の判決は期待のとおりにはいっていないようである。
「誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由がある」とは、実務では厳しく捉えられている。そのため、相当性の理論によって刑事免責を認めた判決はほとんどないとされている。東京地方裁判所1972〈昭和47〉年5月15日判決が、当事者に直接確認をした事案で一部の摘示事実について免責を認め、一部無罪を言い渡している(判例タイムズ279号292頁、平川宗信「記事内容の真実性に関する錯誤」での指摘。メディア判例百選、有斐閣、2005年)。
インターネット上の名誉毀損
上記の判例は報道機関というプロについての判断だが、さてインターネット上で誰でも簡単に表現することができるようになった現在、個人ユーザーによる表現行為についても、上記判決を同様の理論が適用されるのだろうか。それともよりゆるやかな相当性の理論が適用されるのだろうか。
これについても最高裁の決定が出ている(最高裁平成22年3月15日第一小法廷決定)。そこでは、他の表現手段を利用した場合と同様に、行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り、名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって、より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではないと判断されている。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
インターネットでは、ユーザーが気軽に他のサイトの記事を自身のブログに転載したり、他のサイトの記事内容に基づいて推測する記事を書くことがありうる。しかし、もしその他のサイトの記事が虚偽であったならば、確実な根拠なく真実であると誤信すれば名誉毀損の責任を免れない。たとえ匿名で表現をしたとしても、プロバイダーに発信者情報の開示を請求し、表現をした者が誰であるかを突き止めることが可能である。
表現というものは、ときに人を傷つけることがある。それが許されるのは、公共性、公益性を満たし、事実が真実であることについて相当の根拠をもって表現をした場合であることを心にとめておきたい。
相当の根拠が裁判上厳しく判断されすぎているのでないかという問題については、別の記事でまとめてみようと思う。