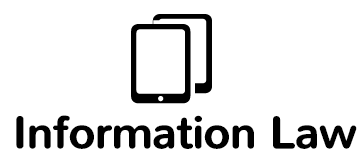亡くなった人に対して名誉毀損は成立するか―『落日燃ゆ』事件
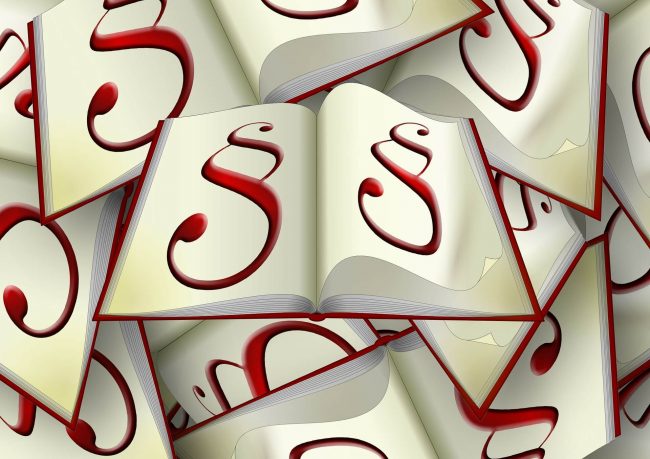
亡くなった人に対する表現について、名誉毀損を理由とした損害賠償請求や謝罪広告請求の訴訟が起こされることがある。表現の対象となっている人はすでに亡くなっており、訴訟を提起することはできない。代わって原告になるのは主に近親者であるが、どのような判断がなされているのだろうか。死者の名誉毀損といわれている論点である。
Contents
リーディングケース『落日燃ゆ』事件
リーディングケースは、作家城山三郎の『落日燃ゆ』をめぐる訴訟である。出版した新潮社のウェブサイトによれば、『落日燃ゆ』は次のように紹介されている。
東京裁判で絞首刑を宣告された七人のA級戦犯のうち、ただ一人の文官であった元総理、外相広田弘毅。戦争防止に努めながら、その努力に水をさし続けた軍人たちと共に処刑されるという運命に直面させられた広田。そしてそれを従容として受け入れ一切の弁解をしなかった広田の生涯を、激動の昭和史と重ねながら抑制した筆致で克明にたどる。毎日出版文化賞・吉川英治文学賞受賞。
本記事の判例として紹介する事件は、この『落日燃ゆ』の中に登場する広田元首相のライバルと目されていた外交官Aをめぐるものである。
事案の概要
小説家城山三郎の著作で、広田弘毅元首相の伝記小説である『落日燃ゆ』の中に、ライバルと目されていた外交官A(故人)の私事に関する記述があった。問題とされた箇所は「それに、相手は花柳界の女だけではない。部下の妻との関係もうんぬんされた。(潔癖な広田は、こうしたAの私行に、『風上にも置けぬ』と眉をひそめていた)」というものだった。
Aには子がなかったが、Aの甥であるX(原告・控訴人)は、この文章は、事実無根であり、広田は潔癖であるが、Aは外務省の部下の妻と姦通をした破廉恥漢として、2人を対照させており、部下の妻との関係の具体的内容が、いかにも反倫理的なものであったかのように推測させ、その噂の内容がかなり現実性をおびているかの如く強調していると主張。Xは、これによってAの名誉が害され、Aを実父のように敬愛してやまないXは、多大な精神的苦痛を受けたとして、城山三郎に対し、謝罪広告の掲載(朝日・毎日・日経の全国紙3社の社会面に3日間継続して掲載)と慰謝料100万円の支払を求めて、東京地方裁判所に訴訟を提起した。
東京地方裁判所は、死者に対する名誉毀損表現について、ⅰ)死者の名誉を毀損する行為により、遺族等生存者自身の名誉が毀損される場合と、ⅱ)死者の名誉が毀損されるにとどまる場合とに区別。
そして、ⅰ)の場合は遺族に対する名誉毀損が成立するが、ⅱ)の場合は虚偽虚妄をもって名誉毀損がなされた場合にかぎり違法行為となると解すべきであると判断の枠組みを提示。
結論として、本件はⅱ)の場合になるが、虚偽虚妄であると認定するに足りる証拠がないとして請求を棄却した(昭和52年7月19日判決)。
Xは、この判決を不服として控訴した。
なお、地裁判決では、城山が取材活動を通じて、Aの公人としての全活動を知り、卓越した有能な外交官であり、広田が一目おいて意識するほどの立派な人物であると評価し、その認識のもとに筆をとり、Aその人のスケールの大きさを正確に伝える努力を払ったと認定している。
控訴審である東京高等裁判所は、控訴を棄却した(昭和54年3月14日判決)。この事件は上告されているが、判例集に登載がないところをみると、結論に変わりはなく、最高裁は上告を棄却したものと考えられる。
控訴審判決判旨
まず死者の名誉ないし人格権についてであるが、刑法230条2項及び著作権法60条はこれを肯定し、法律上保護すべきものとしていることは明らかである。右のほか、一般私法に関しては直接の規定はないが、特に右と異なる考え方をすべき理由は見出せないから、この分野においても、法律上保護されるべき権利ないし利益として、その侵害行為につき不法行為成立の可能性を肯定すべきである。しかし、この場合何人が民事上の請求権を行使しうるかについてはなんらの規定がなく、どの点につき著作権法116条あるいは刑事訴訟法233条1項を類推してその行使者を定めるとすることもたやすく肯認し難い。結局その権利の行使につき実定法上の根拠を欠くというほかない。
ただ本訴は、死者に対する名誉毀損行為により控訴人自らが著しい精神的苦痛を蒙つたとして、控訴人に対する不法行為を主張するものと解されるのであるから、前記のような請求権者の問題はない。そして故人に対する遺族の敬愛追慕の情も一種の人格的法益としてこれを保護すべきものであるから、これを違法に侵害する行為は不法行為を構成するものといえよう。もっとも、死者に対する遺族の敬愛追慕の情は死の直後に最も強く、その後時の経過とともに軽減して行くものであることも一般に認めうるところであり、他面死者に関する事実も時の経過とともにいわば歴史的事実へと移行して行くものということができるので、年月を経るに従い、歴史的事実探求の自由あるいは表現の自由への配慮が優位に立つに至ると考えるべきである。
本件のような場合、行為の違法性の判断にあたり考慮されるべき事項は必ずしも単純でなく、被侵害法益と侵害行為の両面からその態様を較量してこれを決せざるを得ないが、その判断にあたっては、当然に時の経過に伴う前判示の事情を斜酌すべきである。
ところでAは昭和4年11月29日に死亡しているところ、本件文章はその死後44年余を経た昭和49年1月に発表されたものである。かような年月の経過のある場合、右行為の違法性を肯定するためには、前説示に照らし、少なくとも摘示された事実が虚偽であることを要するものと解すべく、かつその事実が重大で、その時間的経過にかかわらず、控訴人の故人に対する敬愛迫慕の情を受認し難い程度に害したといいうる場合に不法行為の成立を肯定すべきものとするのが相当である。
しかして、前認定によれば、本件文章に記載された問題の個所が虚偽の事実と認めることはできないから被控訴人の行為について違法性はなく、控訴人主張の不法行為の成立を認めることはできない。
死者の名誉毀損は法律的にどのように構成されるのか
『落日燃ゆ』事件の前には、死者は人格権を有しないから名誉毀損とはならないという古い判決が1件あったようである(東京地判昭和36年11月20日)。
上記の東京地裁判決は、死者に対する名誉毀損について、東京地裁の昭和36年判決の後に出された最初の判決のようである。他に、臼井吉見の著作『事故のてんまつ』が、川端康成とその遺族の名誉やプライバシーを侵害しているとして、遺族が訴訟を提起した事件があるが、和解で解決しており判決に至っていない。
大別すると2つの説あり
死者の名誉毀損については、大別して2つの説がある。
①死者の人格権が侵害されるという構成を採る見解(直接保護説)と、
②遺族固有の人格権ないし敬虔感情の侵害と構成する見解(間接保護説)
である。
『落日燃ゆ』事件の東京地裁判決も東京高裁判決も、①の死者の人格権が侵害されることによる不法行為の成立の可能性を肯定している。
しかし、結論的には、東京地裁判決は不法行為の成立を否定している。「現行法制の下においては、憲法21条、刑法230条2項、民法709条以下不法行為に関する法条、その他関連の諸法規諸法条に鑑み、死者の名誉を毀損する行為は、虚偽虚妄を以てその名誉毀損がなされた場合にかぎり違法行為となると解すべきであ」るとして、虚偽虚妄の証拠がないと判断した。
もっとも、同判決は、「虚偽虚妄を以てその名誉毀損がなされた場合にかぎり違法行為となると解すべきであ」るという判断のあとに、「故意又は過失に因り、虚偽、虚妄を以て死者の名誉を毀損し、これにより死者の親族又はその子孫(これと同一視すべき者をふくむ。…)の死者に対する敬愛追慕の情等の人格的法益を、社会的に妥当な受忍の限度を越えて侵害した者は、右被害の遺族に対し、これに因って生じた損害を賠償する責に任ず〔る〕」と述べており、死者の名誉毀損それ自体の成立可能性を認めたものであるのか、遺族の敬愛追慕の情の侵害とみるのかが非常に分かりにくくなっている。東京地裁判決を②に分類している文献もある。
これに対して、東京高裁は、誰が民事上の請求権を行使しうるかについてなんらの規定がなく、著作権法や刑事訴訟法の規定を類推することも認めがたいという理由で、請求権はあるものの、実際の行使については実定法上の根拠を欠くと判断している。
東京高裁が死者の人格権侵害について不法行為の成立を認める理由としてあげているのは、死者の名誉毀損罪(刑法230条2項)と、著作権法の規定(60条)である。条文をあげておこう。刑法では、死者の名誉毀損罪の保護法益は、死者の名誉であるのが通説とされている。
(名誉毀損)
第230条
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護)
第60条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
遺族固有の人格権ないし敬虔感情の侵害と構成する裁判例が多い
一般に、人格権は一身専属権(ある人に帰属し、他の人が取得または行使することのできない権利)であり、権利者の死亡によって消滅すると考えられている。裁判例も、前記の②の遺族固有の人格権ないし敬虔感情の侵害と構成するものが多く見られる。
東京高裁判決も、①の行使を否定した後、②の構成で判断をしている。そして、不法行為が成立する要件として、ⅰ)事実が虚偽であり、かつⅱ)侵害が重大であることをあげている。結論的に、それらの証明がないとして控訴を棄却した。
判決のポイント
以上は、法律家の議論であっていささか退屈されたにちがいない。
法律構成も大切なのだが、『落日燃ゆ』事件の高裁判決のポイントは、遺族の敬愛追慕の情に対する侵害を認めながらも、時の経過について考慮を加えた部分ではないだろうか。これは過去の歴史的事実について表現する場合に、表現の自由への配慮をした重要な判示であると思う。再度、引用しておこう。
もっとも、死者に対する遺族の敬愛追慕の情は死の直後に最も強く、その後時の経過とともに軽減して行くものであることも一般に認めうるところであり、他面死者に関する事実も時の経過とともにいわば歴史的事実へと移行して行くものということができるので、年月を経るに従い、歴史的事実探求の自由あるいは表現の自由への配慮が優位に立つに至ると考えるべきである。
本件のような場合、行為の違法性の判断にあたり考慮されるべき事項は必ずしも単純でなく、被侵害法益と侵害行為の両面からその態様を較量してこれを決せざるを得ないが、その判断にあたっては、当然に時の経過に伴う前判示の事情を斜酌すべきである。
『落日燃ゆ』以後の判決
『落日燃ゆ』以後の死者に関する表現をめぐる名誉毀損訴訟の判決として、判例集や文献で確認した限り、次のようなものがある。判決は全部が公開されているわけではないので、他にも判例があるだろう。裁判所のウェブサイトに掲載されている判決については、リンクを張っている。
- 静岡地裁昭和56年7月17日判決
- 大阪地裁堺支部昭和58年3月23日判決
- 東京地裁昭和58年5月26日判決
- 東京地裁八王子支部平成元年11月9日判決
- 那覇地判平成8年1月29日判決
- 大阪地裁平成元年12月27日判決
- 札幌地裁平成14年6月27日判決
- 熊本地裁平成14年12月27日判決
- 大分地判平成15年5月15日判決
- 福岡高判平成16年2月23日判決
- 東京地判平成17年4月13日判決
- 東京地判平成17年8月23日判決
- 東京高判平成18年5月24日判決
- 東京地判平成18年9月26日判決
- 東京地裁平成18年9月26日判決
- 大阪地裁平成20年3月28日判決
- 大阪高判平成20年10月31日判決
- 松山地裁平成22年4月14日判決
- 那覇地判平成22年10月26日判決
- 東京地裁平成22年12月20日判決
- 東京地裁平成23年1月14日判決
- 東京地裁平成23年4月25日判決
- 東京地裁平成23年6月15日判決
- 東京地裁平成25年6月21日判決
- 東京高判平成25年11月28日判決
- 最一小判平成28年1月21日判決
- 東京地判平成28年7月29日判決
これらの判決の中で、作家大江健三郎の『沖縄ノート』についての大阪高判平成20年10月31日判決で、注目すべき判示がなされている。太平洋戦争末期に沖縄で発生したいわゆる「集団自決」を命令したとされた守備隊長X1ないし守備隊長であったAの親族X2が、虚偽の事実により名誉が毀損されたとして、岩波書店に対し出版の差止めの請求を、岩波書店と大江健三郎に対し損害賠償および謝罪広告掲載の請求を行った訴訟の控訴審判決である。この事件は被告の勝訴が確定している。
表現の自由、とりわけ公共的事項に関する表現の自由の持つ憲法上の価値の重要性等に鑑み、原則として同様に解すべきものである。さらに、本件のように、高度な公共の利害に関する事実に係り、かつ、もっぱら公益を図る目的で出版された書籍について、発刊当時はその記述に真実性や真実相当性が認められ、長年にわたって出版を継続してきたところ、新しい資料の出現によりその真実性等が揺らいだというような場合にあっては、直ちにそれだけで、当該記述を改めない限りそのままの形で当該書籍の出版を継続することが違法になると解することは相当でない。そうでなければ、著者は、過去の著作物についても常に新しい資料の出現に意を払い、記述の真実性について再考し続けなければならないということになるし、名誉侵害を主張する者は新しい資料の出現毎に争いを蒸し返せることにもなる。著者に対する将来にわたるそのような負担は、結局は言論を萎縮させることにつながるおそれがある。また、特に公共の利害に深く関わる事柄については、本来、事実についてその時点の資料に基づくある主張がなされ、それに対して別の資料や論拠に基づき批判がなされ、更にそこで深められた論点について新たな資料が探索されて再批判が繰り返されるなどして、その時代の大方の意見が形成され、さらにその大方の意見自体が時代を超えて再批判されてゆくというような過程をたどるものであり、そのような過程を保障することこそが民主主義社会の存続の基盤をなすものといえる。特に、公務員に関する事実についてはその必要性が大きい。そうだとすると、仮に後の資料からみて誤りとみなされる主張も、言論の場において無価値なものであるとはいえず、これに対する寛容さこそが、自由な言論の発展を保障するものといえる。したがって、新しい資料の出現によりある記述の真実性が揺らいだからといって、直ちにそれだけで、当該記述を含む書籍の出版の継続が違法になると解するのは相当でない。もっとも、そのような場合にも、①新たな資料等により当該記述の内容が真実でないことが明白になり、他方で、②当該記述を含む書籍の発行により名誉等を侵害された者がその後も重大な不利益を受け続けているなどの事情があり、③当該書籍をそのまま発行し続けることが、先のような観点や出版の自由などとの関係などを考え合わせたとしても社会的な許容の限度を超えると判断されるような場合があり得るのであって、このような段階に至ったときには、当該書籍の出版をそのまま継続することは、不法行為を構成すると共に、差止めの対象にもなると解するのが相当である。